こんにちは。
練馬区議会議員の佐藤力です。
今回は、私が委員長を務める練馬区議会・文教児童青少年委員会で実施した視察についてご報告します。
視察2カ所目は、大阪府茨木市にある「シェアリンク茨木」を訪問しました。
ここでは、児童養護施設出身者や親を頼れない若者など、社会的支援を必要とする若者たちを地域全体で支える仕組みが構築されています。
単なる居住支援にとどまらず、「支援を受け入れる力(受援力)」や「精神的自立」を重視した支援が行われており、日本の福祉が抱える構造的課題に対して、一つのモデルを示していました。
シェアリンク茨木とは?
「シェアリンク茨木(Share Link 茨木)」とは、大阪府茨木市を拠点とする市民ボランティア団体で、主に子供・子育て・若者支援を目的とした活動をしている組織です。
「喜びや未来をシェア(共有)し、リンク(つなぐ)」という理念のもと、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。
概要・理念
- 団体名:シェアリンク茨木(非営利任意団体)
- 設立:2010年9月から活動開始
- 代表者:辻 由起子(社会福祉士・保育士資格保持者)
- 拠点:茨木市(男女共生センター「ローズWAM」など)
- ミッション:子供・子育て・若者支援を通じて、誰もが孤立しない地域をつくる
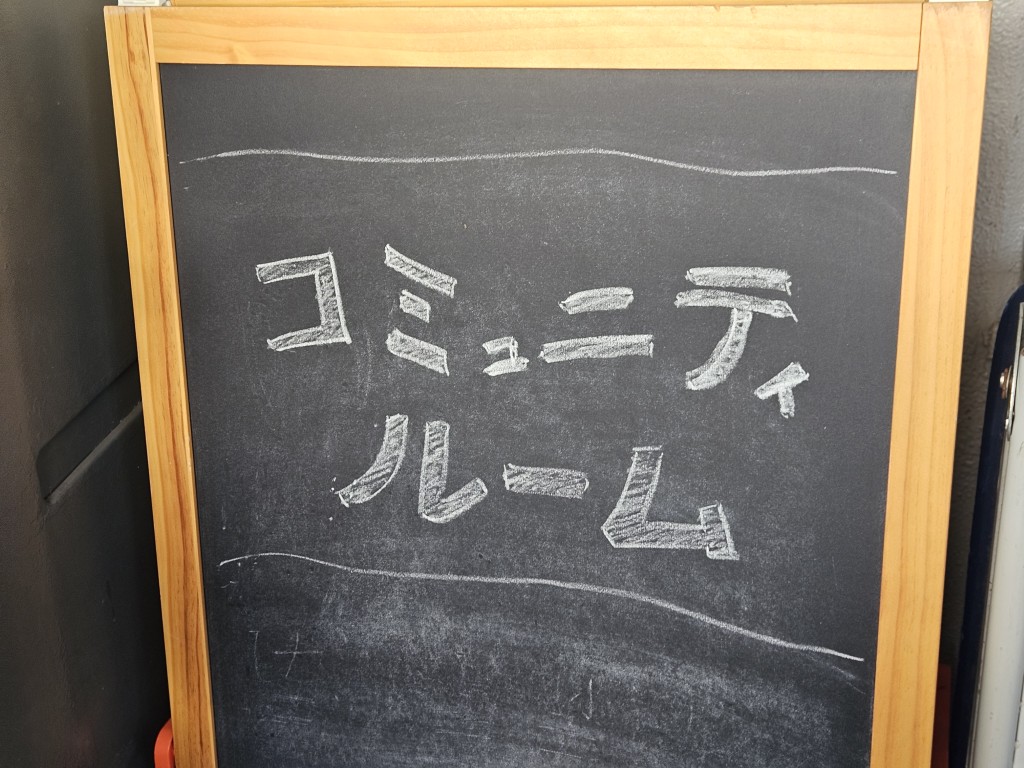
主な活動内容
シェアリンク茨木は多様な活動を展開しています。
| 活動カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 食育 | 「いばらき自炊塾」「みんなの畑」など、土づくり〜収穫〜調理〜加工まで体験できるプログラムを実施。 |
| 居住支援/シェアハウス運営 | 府営住宅の空室を活用した若年女性向けシェアハウスを運営(定員18人・家具家電付き・保証人不要)。 |
| 親子防災 | 「親子防災部」を設け、子育て世代向け防災教育や避難訓練を実施。 |
| 子育て応援 / フード支援 | フードパントリー、子育てイベント、相談支援を通じて生活基盤をサポート。 |
| 相談・講演・政策提言 | 若者支援や居住支援に関する講演会・提言を行政と連携して実施。 |
福祉の課題とシェアリンクのアプローチ
日本の福祉制度は「申請主義」が基本です。
つまり、自ら申請をしなければ支援が受けられない仕組みになっています。
しかし、困難を抱える若者ほど、自分の状況を言葉にして行政用語で説明し、申請手続きをこなすことは難しいのが現実です。
だからこそ、支援側から積極的に関わる「アウトリーチ」が欠かせません。
茨木市では、市単位を越えた「広域的な若者支援」が必要と考え、地域のボランティアや団体が連携し、行政が最小限の支援を行う体制を整えています。
2010年9月、ママたちによる「居場所づくり」から始まったこの取り組みは、今では地域の支え合いモデルとして全国から注目されています。
若者たちが抱える現実と支援の工夫
視察で特に印象に残ったのは、児童養護施設出身者の支援です。
- 「愛されたい」「大切にされたい」という想い
- しかし「大切にされた経験がないため、他人を大切にできない」
- アタッチメント(愛着)形成の課題から、人との関わり方が難しい
「同じ釜の飯を食べる」という言葉が印象的でした。
共に食事をすることで、心のハードルを下げ、信頼関係を築いていく。
自立支援の前に、まずは“生理的欲求”や“安全の欲求”を満たすことが大切だと感じました。
若者たちの抱える多様な事情
現場で聞いた声からは、若者たちの置かれている厳しい現実が見えてきました。
- 親や親族を頼れない
- 昼職に就くためには保証人が必要で働けない
- 奨学金の返済負担
- DVや教育虐待、性の課題
- 発達・精神面での特性を抱えている
こうした状況を踏まえ、シェアリンクではユースクリニックや産婦人科との連携も進めています。
「少年院に入る前の少年の多くは、労働搾取の被害者でもある」――
この言葉が示すように、加害と被害は紙一重。だからこそ、社会全体で支える視点が必要です。
自立支援における「居場所」の力
シェアリンク茨木では、18部屋ある府営住宅のうち、あえて空室を残しています。
それは「今すぐ入らなくても、いざという時に行ける場所がある」という安心感を提供するためです。
また、市内には若者の居場所「ユースプラザ」が5か所設置され、気軽に相談・交流できる体制が整っています。
さらに、新施設「おにクル」では、雨でも集まれる“公園のような居場所”をコンセプトにしています。
ただし、「施設ができたからといって何かが変わるわけではない」という言葉の通り、日常の地道なコミュニケーションと信頼関係の積み重ねこそが何より大切です。
行政と地域の協働モデル
地域のボランティア団体が主体となって支援し、行政は最低限のサポートにとどめています。
「お金がないと続かない事業ではダメ」という茨木市長の言葉に、持続可能な地域福祉の本質が込められていました。
まさに現代版の“家守(やもり)”のように、地域の誰かが誰かを見守り支える文化が根付いています。
今後に向けて:10年先を見据えたまちづくり
シェアリンク茨木の取り組みは、単なる福祉政策ではなく「地域の文化」づくりでもあります。
10年先、20年先を見据え、実証実験を重ねながら、議会や行政の制約を超えて実践を続ける市長の姿勢にも学ぶ点が多くありました。
日本の福祉の未来に必要なのは、「申請主義」を超えた“つながり主義”。
誰もが孤立せず、誰かに頼れる社会へ。
茨木市の挑戦は、その第一歩を示していました。

