おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。
練馬の力を伸ばすために、全力で頑張ってまいります。
今回は、「“寝屋川モデル” いじめゼロに向けた新アプローチ」をご紹介します。
いじめ問題は、どの地域でも決して他人事ではありません。
しかし大阪府寝屋川市では、全国的にも注目される“新しい体制”で、いじめゼロを目指す取り組みを進めています。
教育委員会と市長部局がタッグを組む「二本立ての対応」が特徴です。
私が委員長を務める文教児童青少年委員会で、実際に現地を視察してきましたので、その内容をわかりやすくお伝えします。
目次
1.寝屋川市の概要
寝屋川市は人口およそ22万4千人、平成31年(2019年)に中核市に移行しました。
注目すべきは、広瀬けいすけ市長のリーダーシップです。X(旧Twitter)を通じて市政情報を積極的に発信し、市民アンケートを活用して政策を磨き上げる姿勢が非常に印象的でした。

https://twitter.com/hirosekeisuke_?s=20
教育・福祉・防災など幅広い分野で独自の施策を展開しており、今回ご紹介する「いじめ対策」も令和元年(2019年)にスタートしたものです。
私は練馬区議会の文教児童青少年委員会の委員長として、この寝屋川市の取組を現地で学んできました。
2.“寝屋川モデル”とは?
このモデルの最大の特徴は、教育委員会と市長部局が連携して対応する新しい体制にあります。
令和元年10月に、市長部局の危機管理部内に「監察課」を新設。
「いじめ事件が起きたから」ではなく、“子育て世帯に選ばれるまち”を目指して先んじて設置したことがポイントです。
監察課は教育委員会と協力し、教育的アプローチと行政的アプローチの2本立てで対応しています。
3.監察課の役割と効果
監察課には9名の職員が配置され、うち課長と係長1名が弁護士資格を持つなど、法務の専門知識を活かした実務×法務のハイブリッド体制を確立しています。
いじめ認知件数の推移
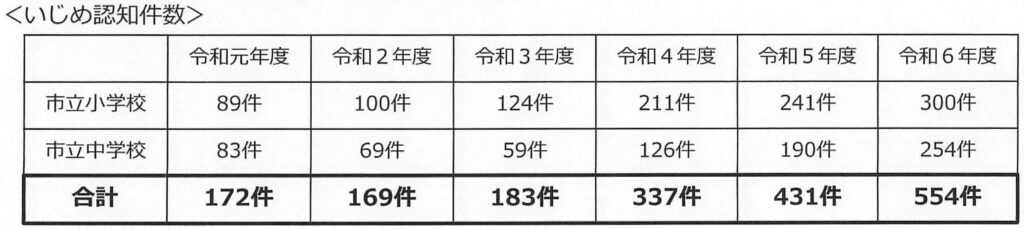
- 令和元年度:172件
- 令和6年度:554件
この増加は、いじめが増えたのではなく、隠れていたいじめを見逃さない仕組みが整った結果です。
監察課への直接相談は186件あり、そのうち97件がいじめと認定されました。
「厳しく対応する」という姿勢を明確にしたことで、相談しやすい環境づくりにもつながっています。
4.「ダブルチェック体制」と“三権分立”
寝屋川市では、教育委員会と監察課が並走して対応することで、次のような効果を生んでいます。
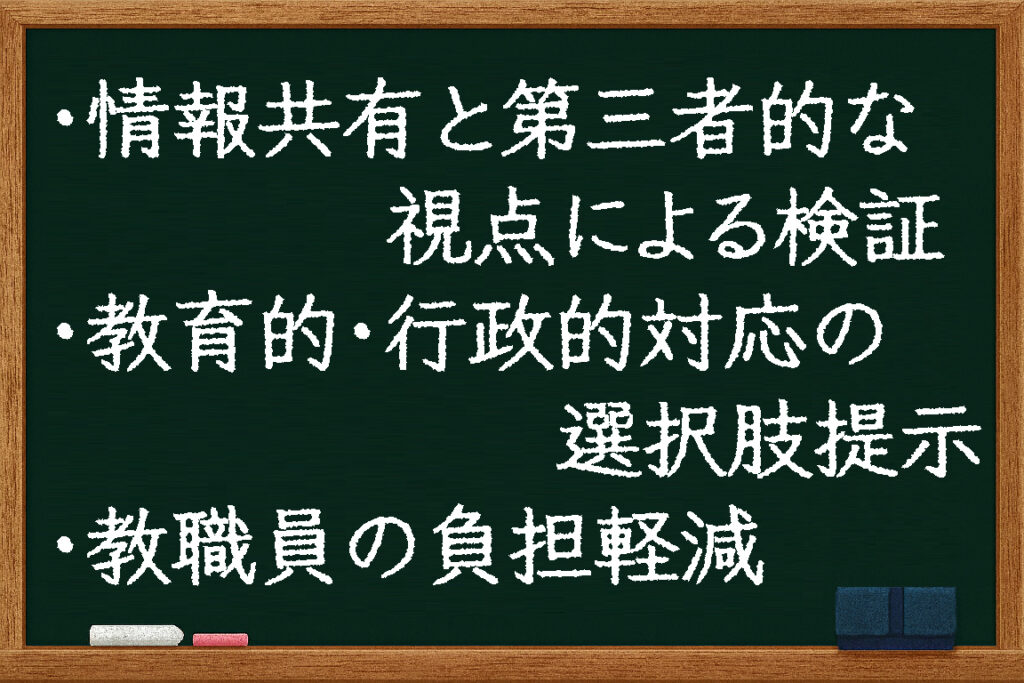
- 情報共有と第三者視点による検証(ダブルチェック)
- 教育的・行政的対応の選択肢拡大
- 教職員の負担軽減
さらに「教育」「行政」「法務」の三つが連携する“いじめ対応の三権分立”を掲げています。
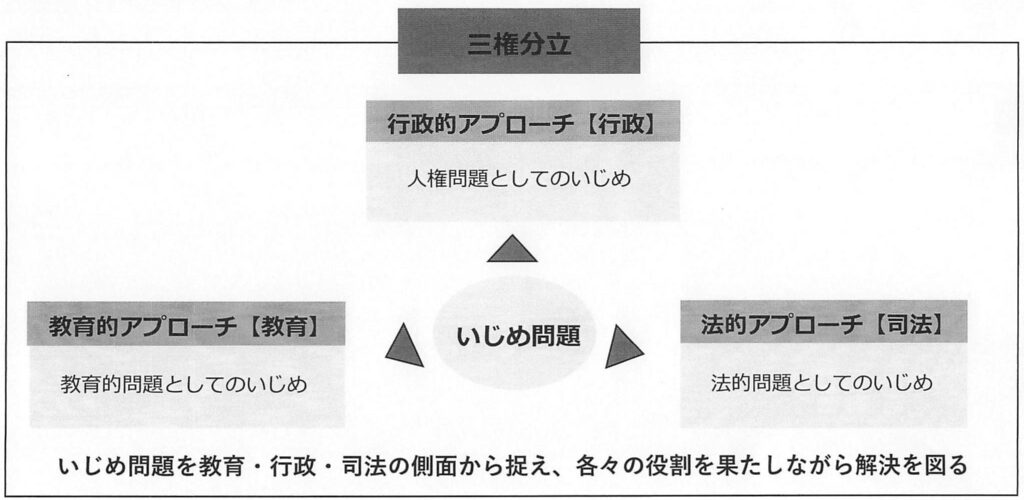
教育委員会による教育的対応、監察課による行政的対応、弁護士による法的支援が連携し、いじめを人権問題として迅速に解決する仕組みです。
また、被害者支援として「いじめ被害者支援事業補助金」も用意され、
弁護士費用・転校費用・被害物の修繕補助などの支援が行われています。
5.練馬区への示唆とまとめ
“寝屋川モデル”で印象的だったのは、教育と行政の二重チェック体制です。
教育委員会や学校だけでは、子供や保護者との関係性が深いため、いじめ対応が慎重になりすぎ、対応が遅れる場合があります。
しかし、市長部局が関与することで、より客観的かつスピーディーな対応が可能になります。
練馬区でも、次のような取り組みが必要だと感じました。
- 第三者的視点を取り入れたダブルチェック体制
- 行政・教育・法務の連携強化
こうした仕組みが、いじめの早期発見・早期対応につながると強く感じています。
おわりに
いじめは、子供の命や尊厳に関わる重大な人権問題です。
寝屋川市のように、教育・行政・法務が一体となる仕組みを整えることが、子供を守る第一歩になります。
練馬区でも、子供たちが安心して学校生活を送れるよう、全力で取り組んでまいります。

