おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。
スマートフォンやモバイルバッテリーなどに搭載されている リチウムイオン電池の火災事故が、今まさに急増しています。
特に「膨張」は重大事故につながる危険なサイン。
今回は、事故の現状から原因、火災を防ぐ対策、そして練馬区で新たに拡充された回収場所まで、5つのパートに分けて分かりやすくご紹介します。

目次
1.現状
リチウムイオン電池を搭載したスマートフォン・モバイルバッテリー・家電製品の普及に合わせ、火災事故は急増しています。
東京消防庁によれば、過去10年間で約10倍に増え、都内では令和6年に過去最多の230件を記録。全国では年間2万件超とも言われています。
・出火要因(不明除く)は、
1位:分解・廃棄(21%)
2位:落下など外部の衝撃(21%)
3位:通常使用中の出火(10%)
と続いています。
・特に危険なのが就寝中の無監視充電。異常の発見が遅れ、延焼リスクが高まります。
・また、火災原因として多いのが正規品以外の充電器・ケーブルの使用です。
2.なぜ“膨張”が危険なのか(出火メカニズム)
リチウムイオン電池は内部が見えませんが、膨張=ガスが発生するほど劣化や損傷が進んでいる状態です。
内部で短絡(ショート)が起きると、
ショート → 熱暴走 → 発熱 → 発煙 → 発火
という流れで、一気に危険性が高まります。
▼要注意サイン
・膨張
・異臭
・異音
・異常な発熱
これらを感じたら、直ちに使用中止・充電中止・隔離。
穴を開ける、押し潰す、分解するなどは絶対にNGです。
3.出火の原因
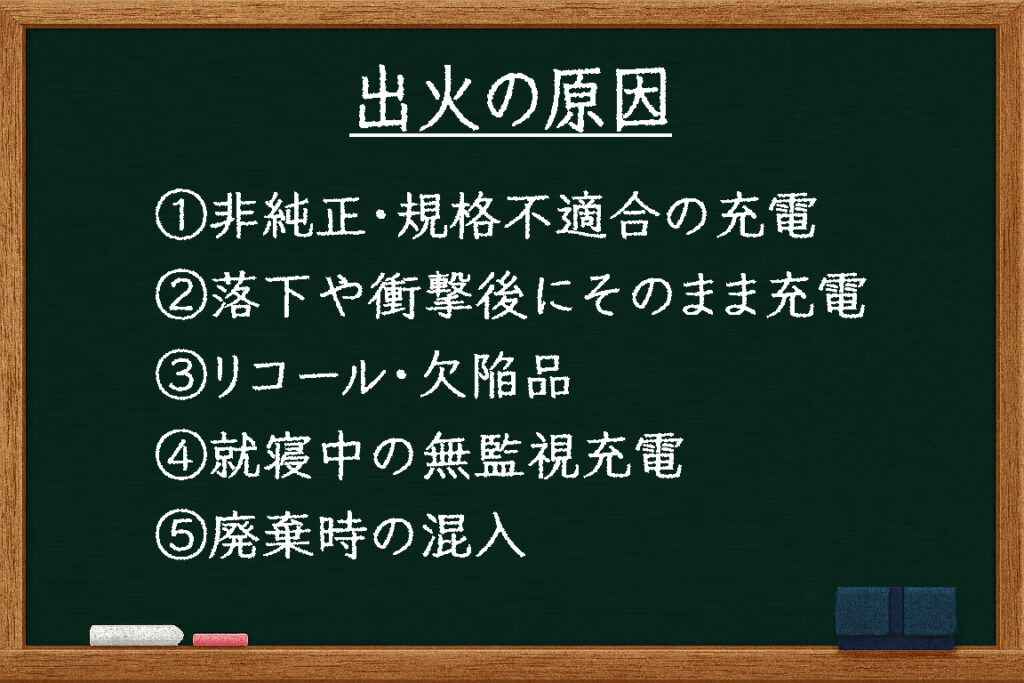
- 非純正・規格不適合の充電器
出力不一致で過充電となり発火のリスク。 - 落下・衝撃後にそのまま充電
内部損傷が短絡につながる。 - リコール・欠陥品
予兆なく発火するケースも。 - 就寝中の無監視充電
初期対応が遅れ、延焼しやすい。 - 廃棄時の混入
圧縮作業中に発火し、ごみ収集車・清掃工場火災の原因に。
全国で年間約8,500件発生。
4.火災を起こさないための対策
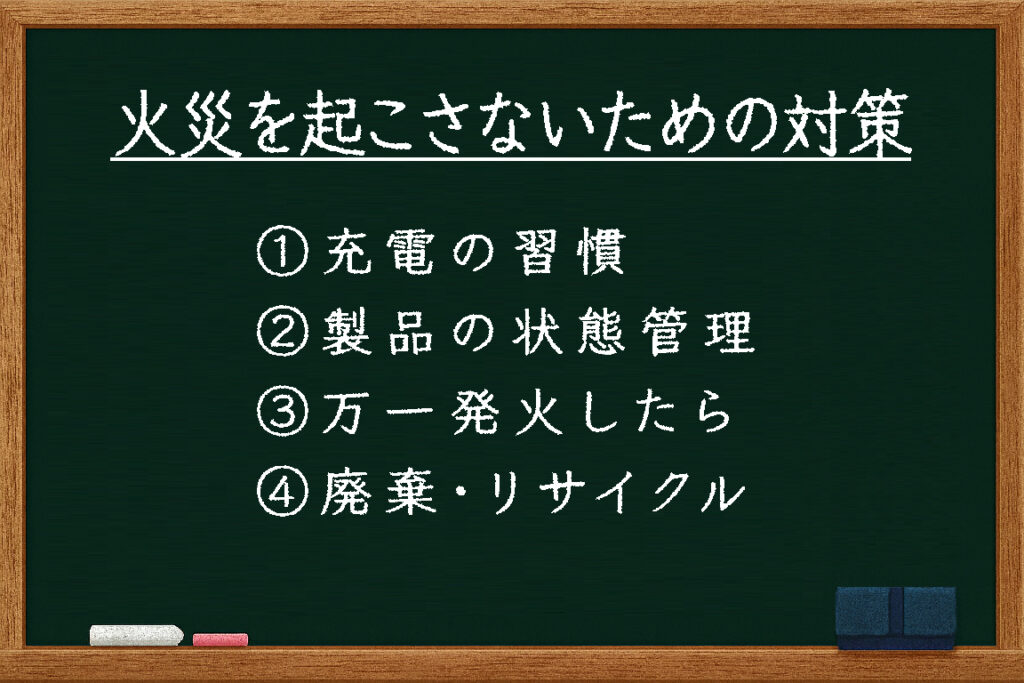
① 充電時の注意
- 就寝中の充電は避ける。
- どうしても行う場合は、金属・タイル等の不燃性の台に置く。
- PSEマーク、メーカー純正の充電器・ケーブルを使用。
- 充電中は温度や異臭を確認し、異常があればただちに中止。
② 製品の状態管理
- 膨張・ひび割れ・液漏れ・異臭があれば使用中止。
- 車内放置・高温多湿・直射日光を避ける。
- リコール情報の定期確認(メーカー・NITE・消費者庁)。
③ 万一発火したら
- 怖がらずに水をかける(リチウム“イオン”電池には水が有効)。
- 可能なら水中で冷却を継続。
- 危険を感じたらすぐ119番。
④ 廃棄・リサイクル
- 一般ごみには絶対に混ぜない。
- 端子をテープで絶縁し、販売店や自治体の回収拠点へ。
5.練馬区の回収場所
火災事故が増加する中、練馬区では今月から回収拠点が大幅に拡充されました。
これにより、より安全で便利に回収できるようになりました。
▼増設された常時回収場所
- 関町リサイクルセンター(関町北1-7-14)
- 春日町リサイクルセンター(春日町2-14-16)
- 豊玉リサイクルセンター(豊玉上2-22-15)
- 大泉リサイクルセンター(大泉学園町1-34-10)
- 練馬区資源循環センター(谷原1-2-20)
▼従来の持込先(継続)
- 練馬清掃事務所(豊玉上2-22-15)
- 石神井清掃事務所(上石神井3-34-25)
これまでは清掃事務所への持参や、不燃ごみ収集日に作業員への手渡しが必要でした。
しかし回収拠点が増え、利便性が大きく向上しています。
火災事故を未然に防ぐため、ぜひご活用ください。

