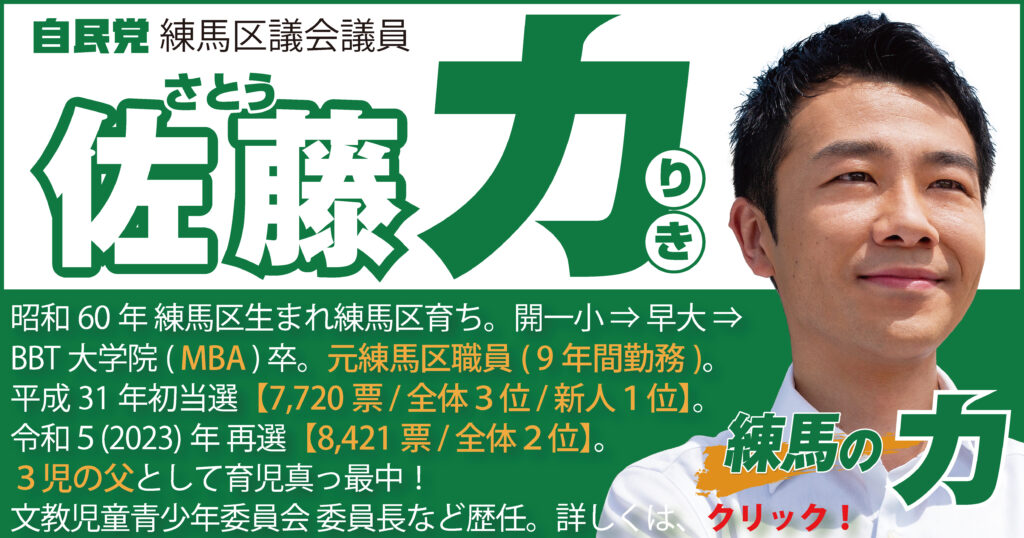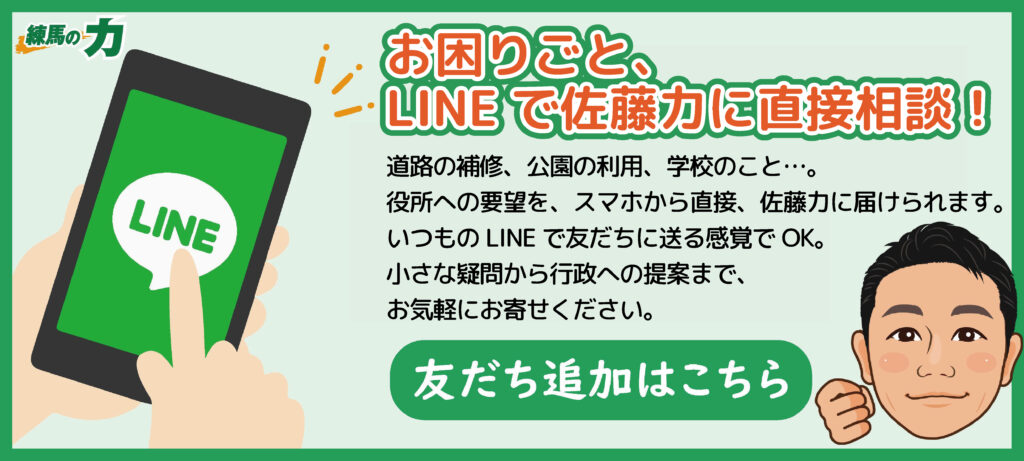おはようございます。
練馬区議会議員の佐藤力です。
今回は、育児が困難な事情を抱える親が、匿名で新生児を託すことができる「赤ちゃんポスト」について解説します。
2025年4月時点で日本国内に3カ所設置されているこの制度は、子供の命を救う“最後の砦”とも言える存在です。しかし、匿名性と「出自を知る権利」の対立、設置の難しさ、運営費用の課題など、多くの課題も抱えています。
本記事では、国内外の事例や制度の違い、自治体の関与、そして社会全体で取り組むべき課題について、わかりやすくまとめました。
🗂目次
1. 赤ちゃんポストの概要と現状(日本国内)
赤ちゃんポストは、親が育児を続けられない事情を抱えた場合に、匿名で赤ちゃんを安全に託せる施設です。
2025年4月現在、日本では以下の3施設に設置されています:
- 熊本市・慈恵病院(2007年~):「こうのとりのゆりかご」
- 東京都墨田区・賛育会病院(2025年3月~):「いのちのバスケット」
- 北海道当別町・こどもSOSほっかいどう(2022年~):「ベビーボックス」
これらの施設は24時間体制で対応し、赤ちゃんが置かれるとセンサーで職員に通知される仕組みです。事前に警察などと調整されており、法律的に問題が起きないよう対応されています。
2. 赤ちゃんポストが直面する課題
最も大きな課題は「匿名性」と「子供の出自を知る権利」の対立です。
国連「子どもの権利条約」では、出自を知ることが子供の権利として保障されています。しかし、日本では親の匿名性が優先されがちで、この権利が損なわれる可能性もあります。
また、赤ちゃんポストの設置には多くの障壁があります。例えば関西地方では設置を目指すNPO法人の努力が実を結ばず、いまだ設置に至っていません。
さらに、国からの運営費補助がないため、継続的な運営には財政支援が必要です。
3. 海外の事例と日本との違い
ドイツでは、赤ちゃんポストの課題に対応するため「内密出産制度」を2014年に導入しました。
この制度では、妊婦は相談機関にのみ実名を明かし、仮名で出産します。子供は16歳になると、生みの親の情報を照会できます。
日本でも、熊本市と墨田区で内密出産が可能です。2022年には厚労省と法務省がガイドラインを公表し、医療機関に母親の情報の永年保存や、戸籍作成についてのルールが示されました。
4. 地方自治体の役割
地方自治体には主に以下の役割があります:
- 戸籍の作成:戸籍法に基づき、匿名であっても子供の戸籍を作成
- 一時保護:児童相談所による赤ちゃんの保護
例えば東京都では、赤ちゃんが預けられた際に児童相談所の職員が現場に駆けつけ、母親と話す機会を持ち、行政支援制度などを丁寧に案内しています。
5. 社会として取り組むべき課題
赤ちゃんポストは「命を守る最後の手段」ですが、その前段階の支援も不可欠です。
- 妊娠初期からの継続的な支援
- 若年層への性教育・避妊啓発
- 経済的困窮への支援
また、法整備が遅れており、赤ちゃんポストは法的にもグレーな存在です。今後、より明確な制度設計が求められています。
6. まとめ:命を守るために私たちができること
赤ちゃんポストは、深刻な事情の中で命をつなぐための大切な制度です。
一方で、制度の裏には複雑な倫理・法・財政の課題が山積しており、簡単な解決策はありません。
私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、支援の輪を広げていくことが、社会全体の課題解決につながります。